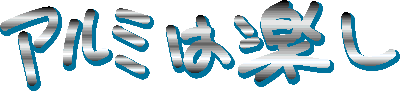
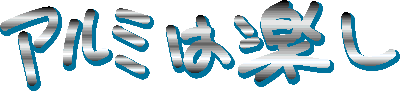
バスボートに絶対に付いていてアルミボートに無いモノってのは色々ありますが、トーナメントをするにあたって絶対に必要なモノは言わずと知れた「ライブウェル」です。
当たり前なんだけどバスを生かして持って帰って、さらには計ってナンボの世界ですから。
そのためにライブウェルに求められる性能ってのは結構シビアなんです。ただ水を溜めれば良いというモノでもありません。よくクーラーボックスに水を溜めただけのライブウェルを使っている人がいますが、これは結構危険です。
ってのも水を循環させることが出来ないからです。バスを元気に管理するために重要な事は、「水中酸素、水の鮮度、水の温度」です。これのどれかが欠けてもバスの衰弱は進みます。
クーラーボックスをライブウェルにする場合は、中の水をポンプで汲み上げて水面に落とすことで水中の酸素を供給することが出来ます。いわゆるぶくぶくポンプも酸素供給の点で同じです。
しかし、この方法では「水の鮮度と水の温度」はコントロール出来ません。そのため、バケツなどによって水を汲み代える必要があるのです。これを怠るとバスは速攻で弱ってしまいます。でも。トーナメント中に水を汲み代えるのは「ものすごくメンドウ」なんですねぇ。
そんな時間があればキャストしちゃおう、と考えてバスを弱らせてしまい、結局デッドフィッシュになってしまったこともありました。やっぱり何はなくとも循環式のエアレーションは必須です。外からの水を補給して鮮度と温度を保ちつつ酸素の補給まで出来るのですからね〜。
んで、この場合は二つの選択肢が有ります。
○一つは、クーラーボックスなどを利用して循環式のシステムを作る。
これは多くのトーナメンターが使用しています。クーラーボックスからポンプを出して水面に落とし、循環させるのです。作りやすいのが利点ですが、水を外に落とすための工夫が必要なのが難点です。
○もう一つは、アルミボートに内蔵してしまう作戦。
あまり実践している人は居ませんが、デッキが広く使えるし組んでしまえば手間いらずなので便利とは言えます。重量は増えるのでカートップには覚悟が必要なうえに艇体に穴をぶち開ける事になるのでそれなりの知識は必須です。私は迷わず内蔵作戦を選択しました。クルマで移動する際の荷物を減らすことが出来るし、狭いデッキをクーラーボックスで占領されたくはありませんので。しかも今回は中古艇。穴なんかいくら開けても惜しくはない(^_^;
その具体的な方法は以下の通り。
こんな感じでセンターシートに内蔵してしまうのです。ポンプはトランサムに固定します。
シートに入っていた浮力体は抜いてデッキ下に移動し、シートの底と側板をアルミ板で作ってアルミアングルで固定すると箱の出来上がり。
ポンプはトランサムに穴をぶち空けて固定します。常時水面下にあるように出来るだけ下に。ネット(フィルター)はゴミ避けとして必要です。これがないとアッと言う間にポンプが壊れちゃうよ!
上の写真では上に見えるのが吸水ポンプで、下のヤツはビルジポンプ。両方とも1時間当たり500ガロンの吐出力があります。ライブウェル用で有ればもうちょっと小さくても大丈夫ですがビルジポンプはでっかい方がいい!近いウチに750ガロンのポンプに交換する....予定。
配水管はお風呂用の配管です。水が漏れないように適当にシリコンコーキングを使ってガッチリと固定します。写真では側舷に空けた穴が写っていますが、これは水面より上に出ます。ライブウェルの水面より下に有ればもっと下方でもいいんだけど強度的な問題を考えるとこの辺が良いかな?ってな気がする(^_^;
特に気を付けるべき事は、水面下に来るモノの防水と耐久性です。この場合はポンプですが、この配管が釣りをしているときに外れてしまったら、ばりばり浸水してこの船は沈みます。ポンプ自体が壊れてビヒが入ってもこれまた危険。
配管はクリップベルトをびしっと使えばまず外れることはありませんがポンプ自体の破損は交換以外にはありません。少しでもラクできるようにカートリッジ式のポンプを選びました。
ついでに在るととても便利なライブウェルタイマーも組み込みます。これはポンプの作動を5分休んで1分動かすように出来るので節電にとっても役に立つのです。ポンプ自体の消耗も低く押さえられるのでオススメのアイテムですね。バスボートには大抵付いてるけど、カートップのアルミボートでタイマーまで奢っている人は少ないだろうなぁ、きっと。
でもねぇ、欠点もあるんだね。これ自体が壊れてしまうという。。。(*_*)
当然ポンプは動かなくなってパニックになったりして。しかもトーナメント中に起こるというなんとかの法則。大抵の場合は中に入っているヒューズが切れる事が原因ですが、サビから来る接触不良などもあります。が、考えてるとキリがないのであまり気にしないことにしよう。最悪の場合は消火バケツで汲めばいーんだ。
つづく
|戻る|次へ| itaru's_page/Copyright ITARU KATSURAGAWA
Web Designed by ITARU KATSURAGAWA